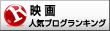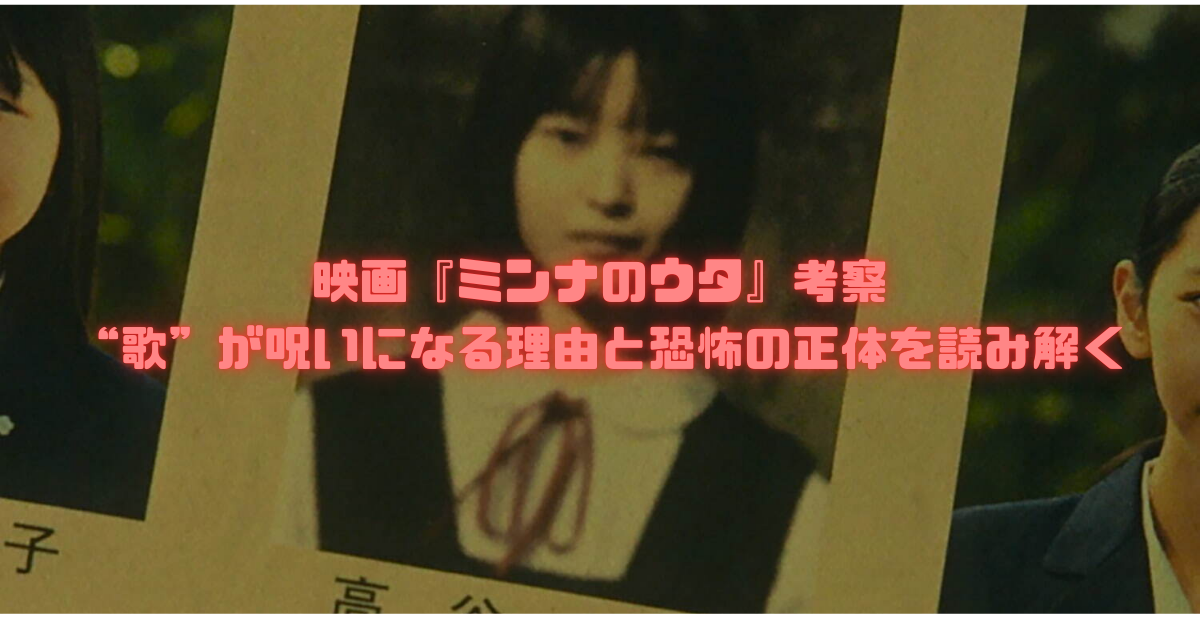
映画『ミンナのウタ』は、怪異そのものよりも「それがどのように広がるか」に重点を置いたホラー作品である。本作の恐怖は、目に見える怪物や明確なルールではなく、曖昧で説明しきれない不安として描かれている。
『ミンナのウタ』 (2023)
— らいとぶらいと (@lightbright0817) 2025年12月24日
清水崇らしいと言えばらしいし、らしくないと言えばらしくない異色作だった。まずGENERATIONSのメンバーが全員本人役で登場するという設定から面白いし、少しずつ情報が開示される事で登場人物達の印象が二転三転するのが良かった。ループ演出怖すぎるのでぜひ見てほしい。 pic.twitter.com/eF9LOSApXq
“歌”が呪いになる理由
物語の中心にあるのは“歌”という存在だ。歌は本来、人と人をつなぐためのものであり、感情を共有するための文化的な道具でもある。しかし本作では、その性質が反転し、呪いを媒介する装置として機能している。
この作品における歌は、「聴いてしまう」「知ってしまう」「口ずさんでしまう」ことで関与が成立する。つまり、意図や善悪とは無関係に、関わった時点で当事者になってしまう構造を持っている。これは従来のホラーに多い“呪いのルール”よりも、はるかに日常に近い。
特定の行動をしたから呪われるのではなく、日常の延長として触れてしまう点に、本作特有の不気味さがある。ラジオ、音声、記憶といった誰にでも開かれた媒体が、恐怖の入口として機能することで、観客自身も無関係ではいられなくなる。
また「ミンナのウタ」というタイトル自体が強い皮肉を含んでいる。みんなのもの、誰のものでもあるはずの歌が、結果的に誰にも責任を取られない呪いとして存在しているからだ。共有されることで力を持ち、同時に責任の所在が曖昧になる構造が浮かび上がる。
作中で描かれる怪異は、強い意思を持った存在というより、「忘れられた感情」や「置き去りにされた声」が形を持ったものとして表現されている。誰にも聞かれなかった思い、気づかれなかった痛みが、歌という形で残り続けているとも読める。
そのため本作の恐怖は、復讐や怒りといった単純な感情だけでは説明できない。むしろ、無関心や傍観、見過ごされてきたことへの歪んだ反動として描かれている。誰かが悪意をもって生み出した呪いではなく、誰も止めなかった結果として生まれた怪異なのだ。
歌が「消せない」存在として描かれる点も重要である。データを消しても、音源を壊しても、完全には終わらない。これは怪異が物理的なものではなく、人の記憶や意識と結びついていることを示している。
一度知ってしまったもの、聞いてしまったものは、完全にはなかったことにできない。そうした不可逆性が、作品全体にじわじわとした後味の悪さを残す。
ラストで明確な解決が提示されないのも、この構造と一致している。問題は解決されず、怪異は封印も浄化もされない。ただ「続いている」ことだけが示される。その終わり方によって、物語は観客の現実と地続きになる。
観終わったあとに歌を思い出してしまう、頭の中で旋律がよみがえる。その瞬間、観客自身もまた物語の構造に組み込まれてしまう。これこそが『ミンナのウタ』の仕掛けている最大の恐怖だと言える。
本作は、派手なショック表現ではなく、「共有」「拡散」「無自覚な加担」といった現代的なテーマをホラーとして再構築している。誰もが加害者にも被害者にもなりうる、その曖昧さが作品全体を覆っている。
『ミンナのウタ』というタイトルは、やさしい響きとは裏腹に、責任の所在が溶けていく社会そのものを指しているのかもしれない。みんなのものだからこそ、誰も止めない。誰のものでもないからこそ、終わらない。その構造自体が、この映画の核心的な恐怖である。
恐怖の正体
映画『ミンナのウタ』の恐怖を語るうえで欠かせない存在が、高谷さなである。本作において彼女は単なる被害者や幽霊として描かれているわけではなく、物語全体の構造そのものを支える象徴的な存在として位置づけられている。
高谷さなは、生前から周囲との関係が断絶した状態にあり、強い孤独を抱えていた人物として描かれる。誰かに助けを求めることも、本音を受け止めてもらうこともできないまま時間が過ぎ、その存在は次第に周囲から見えなくなっていった。
彼女が残した「歌」は、その孤立の中で生まれた唯一の自己表現だったと考えられる。言葉としては届かなかった感情が、旋律という形を取ることで外に漏れ出した。それが後に“呪い”として機能してしまう点に、本作の皮肉がある。
重要なのは、高谷さなが明確な悪意をもって他者を呪おうとした存在として描かれていない点である。彼女の行動原理は復讐というより、「気づいてほしい」「忘れないでほしい」という切実な欲求に近い。
そのため、歌は攻撃というよりも“接続”の手段として広がっていく。聴いた人の意識に入り込み、記憶の中に居場所を作ることで、存在を保とうとする。高谷さなは、自分を覚えてくれる人を探し続けているとも解釈できる。
作中で歌が止められないのは、高谷さなの意思が強いからというより、「忘却そのもの」が許されていない構造にあるからだ。誰にも顧みられずに消えていった存在を、社会がなかったことにしてしまう。その歪みが、怪異という形で表出している。
高谷さなの存在は、特定の個人というより、“見過ごされてきた声の集合体”として読むこともできる。彼女一人の物語でありながら、同時に多くの無名の声を背負っている存在なのだ。
そのため、彼女の歌は一度広がると止められない。誰かが聞き、口ずさぎ、記憶するたびに、新たな媒介が生まれる。この連鎖は、悪意ではなく無関心と無自覚によって支えられている。
作中で明確な救済が提示されないのも、高谷さなの存在が「解決されるべき事件」ではなく、「向き合われるべき問い」だからだ。彼女は成仏する対象ではなく、社会が抱え続けてきた歪みの象徴として残されている。
ラストで歌が再び流れる演出は、高谷さなが消えたことを示すものではない。むしろ、物語の外にいる観客に向かって、その存在が引き継がれたことを示している。観る者が歌を記憶した時点で、彼女は再び“思い出された”ことになる。
この構造によって、『ミンナのウタ』は単なる怪談では終わらない。高谷さなは恐怖の象徴であると同時に、忘れられた声そのものとして、観客の中に居場所を得る。
タイトルが示す「ミンナのウタ」とは、誰かの所有物ではないという意味であり、同時に“みんなが背負ってしまうもの”という皮肉でもある。高谷さなの歌は、共有された瞬間に個人の問題ではなくなり、社会的な現象へと変化する。
このように見ると、本作の恐怖の正体は幽霊ではなく、無関心の連鎖であり、見過ごされてきた感情の蓄積である。高谷さなという存在は、その象徴として物語の中心に置かれている。
『ミンナのウタ』は、高谷さなという一人の少女を通して、「忘れられることの暴力」と「共有されることの怖さ」を描いた作品だと言える。歌が終わらない限り、その問いは観る者の中に残り続ける。
以上。
ブログランキング参加中!
1日1回ポチッと応援よろしくお願いします♪








![[ctunk] NFCキーホルダー 音楽キーホルダー 推し活 カセットテープ 1個 (ピンク) [ctunk] NFCキーホルダー 音楽キーホルダー 推し活 カセットテープ 1個 (ピンク)](https://m.media-amazon.com/images/I/41brJhoeZzL._SL500_.jpg)

![ミンナのウタ 豪華版(数量限定生産)(本編Blu-ray1枚+特典DVD1枚) [Blu-ray] ミンナのウタ 豪華版(数量限定生産)(本編Blu-ray1枚+特典DVD1枚) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/31DXQwrPG2L._SL500_.jpg)
![ミンナのウタ 豪華版(数量限定生産)【Blu-ray】 [ GENERATIONS ] ミンナのウタ 豪華版(数量限定生産)【Blu-ray】 [ GENERATIONS ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7885/4988105107885.jpg?_ex=128x128)